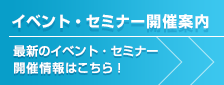フェア・ファイナンス・セミナー ポートフォリオ低炭素化の最前線 ~動き始めた日本の金融機関~
先月、A SEED JAPANが運営団体をしているFair Finance Guide Japan(FFGJ)は、海外の石炭火力発電プロジェクトに対する日本の民間金融機関からの投融資実態について、ケース調査報告書にまとめて発表しました。それに合わせて、7月12日に、石炭への投融資を含めた、金融の業界における社会の低炭素化に向けた取り組みの現状の把握・今後の発展の議論を目的として、金融機関・NPO/NGOなど様々なステークホルダーの皆様を迎えてセミナーを行いました。
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による国連責任投資原則(PRI)への署名や海外の主要金融機関による石炭産業からのダイベストメントの動きなど、金融の業界において「環境・社会・ガバナンス」(ESG)に配慮した投融資を行おうとする流れが加速しています。その一方で、FFGJのレポートにもある通り、日本の金融機関からの石炭産業への莫大な資金の流れは続いています。
そのような状況において、世界の金融がどのような方向に向かおうとしているのか、金融業界はどう環境・社会の価値向上に貢献できるか、そして日本の金融機関はどうあるべきでそれに私たちはどう行動できるか、専門家の方々からのお話を中心に深く考えることができました。
ここではゲストの皆様のご講演とその後の質疑応答についてその内容をご報告します。
講演1.オルタナ総研所長/首席研究員・ニッセイ基礎研究所客員研究員 川村雅彦氏
「ESG投資、投資ポートフォリオの脱炭素化の最新動向について」
<ESG投資に関する近年の動向>
川村氏によると、近年、誰にどう投資するかを考えるSRIから、投資家・投資そのものの環境・社会的影響を考えるESG投資へと金融業界の流れが変化しているといいます。実際に、ESG投資額がここ4, 5年のうちに世界全体で1.7倍に増加し、プロの運用のうちESG投資が総額の1/4を占めるようになりました。今後投資プロセスの意思決定にESG投資を入れていく傾向が一層強まると考えられています。
お話の中で特に印象的だったのは、ESG投資が重視されるようになっているこの流れは、従来の金融業界の常識から考えると、パラダイムシフトが起こったようなものだ、ということです。というのも、かつてESG投資は、短期的には投資の最大化に邪魔であるため受託者責任に反する、とされてきました。しかし、現在は転換が生じ、長期的にESGを考慮しないと受託者責任に反する、とされるようになったのです。
実際の動きとして、世界で1756の機関がPRIに参加しており、日本でも、ESG考慮が被保険者の長期的な利益につながる、としてGPIFが署名したのを皮切りに、56機関が署名を行なっています。また、アメリカ労働省による年金運用のための法律(エリサ法)においても、20年にも及ぶ長い議論の末、ESGは運用の際考慮すべき適切な要素であると明確に位置づけられました。
<金融業界における低・脱炭素化の背景>
まず昨年パリ協定において2℃ターゲット、つまりCO2濃度450ppm目標が設定されました。その達成のためにはカーボンニュートラル(排出量と吸収量のバランス)を目指さなければならず、結果として過去からの積算として排出量の上限が決定されることになります。そうすると利用できない化石燃料が存在することになり、それらは資産価値がなくなる、つまり座礁資産となってしまいます。もし金融機関が化石燃料に投資を続けてしまうと、いつかカーボンバブルがはじけて投資が回収できなくなる可能性が高まっています。そのため、化石燃料、特に気候変動への影響の大きい石炭からの投資の引き揚げ(ダイベストメント)が進んでいるのです。
こう行った考えに基づいて、先月発表されたG20のTCFD(金融安定理事会の気候関連財務情報開示タスクフォース)では、金融機関が分かるように企業のリスクと事業チャンスの両側面を財務インパクトとして発表すべき、と提言されました。そしてノルウェーやカリフォルニアの年金基金を始め、日本以外の金融機関の多くが石炭からのダイベストメントの実施を宣言しており、エクソンモービルが主に資金供給を行なっているロックフェラー財団でさえも、気候変動に対するリスクへの対応を毎年公表すべき、との議決が採択されました。そのような世界の流れがありながら、日本の政府や金融機関は石炭のリスクを直視せず、投融資を進めているのです。
<投資機関のポートフォリオの低・脱炭素化に向けた具体的な取り組み>
そもそも、環境・倫理に配慮することよりも、純粋に財務リスクを低減するためにポートフォリオの低・脱炭素化を行うことが必要である、との認識が金融機関にあるため、自らの投資によって生じうる炭素排出量を計算する必要性が高まっています。先に述べたTCFDの提言を始め、スチュワードシップ・コードでも金融機関が気候変動リスクについて勉強・理解することが必要だとされています。
また運用機関の間での取り決めとして、投資によるCO2排出がいくらか公表するモントリオール・カーボン・プレッジ(炭素誓約)が定められ、消費者ではなく投資家の環境影響・意思決定が問われるようになっています。さらに実践的に、脱炭素化に向け行動する企業の連合である脱炭素連合ができています。
社会全体の今後の流れとして、金融業界によるESG投資と、それを受けた企業側のCSR、ひいてはESG経営とが進んでいく中で、お互いの方向性の確認のために金融業界と企業のESGに関する対話が一層重要になっていくだろうとおっしゃっていました。
講演2.りそな銀行信託財産運用部グループリーダー 松原稔氏
「投資家、特にESG投資家が何をどのように考えて行動しているか」
<ESG投資が進んだ背景>
そもそも松原氏は、2003年のりそなショック(自己資本比率の低下を受けた公的資金の注入の事態)を受けて、社会にどのように貢献していくか考えるようになったそうです。そして2006年にPRIが制定され、社会にとって必要な運用機関となる、つまり儲かることだけでなく世の中の利益になるような投資をするには責任投資が必要だ、との考えに至ったといいます。ただ、かつて銀行の常識は社会の非常識である、と言われてきたように、金融業界においてESG投資は軽視されてきました。その中でGPIFのPRI署名は、社会的にESG投資を促進する起爆剤となる可能性があり、SRI・ESG投資家にとって重要だと考えられています。
また、かつては超短期的な足元の損益のみ熟慮されてきましたが、リーマンショックを受けて、長期的な視野で、お金だけでなく物事の考え方も重要な観点となるという点で、ESG投資が広がっているとも考えられています。さらに、ESG投資によって、長期リスクの低減や社会に必要とされることによる企業成長力の向上、といった効果が生じることで株価の上昇にも繋げられることから、投資家にも受け入れられています。
<りそな銀行が行なっている具体的な取り組み>
まず、どのESG課題を評価するか、世界経済フォーラムなどを参考に、3つのリスク要素として気候変動・サプライチェーン・取締役構成、それにパーム油とコラプションを加えた5つのマテリアリティーを選定し、それらの分野に関して企業活動の評価を行なっています。評価が低い企業に対しては、株主としてその改善を求めて取締役選任・報酬・買収防衛策への議決権を行使できますが、その行使より前に企業側からの働きかけを受け、ESG課題について対話を行なっています。
具体的に、気候変動に関する、特に座礁資産のリスク・機会の評価などについて尋ねる質問状を企業に送付し、その回答をもとに情報を開示し、対話を行なっています。またサプライチェーンについては、国連ビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)に参加しているため、その分野について評価し企業と対話しています。さらに、りそな銀行としてESG投資を継続・強化していくための仕組みとして、毎週会社のマネジメントの方々と責任投資ミーティングを開き、環境・社会・ガバナンスの状況などを議論なさっているそうです。
最後に、
「私たちは、地球を先祖から受け継いだのではなく子供達から借りているのです。」
というネイティブアメリカンの教えを引き合いに、ESG投資・PRI活動を行うにあたっての矜持を示してくださりました。
講演3.「環境・持続社会」研究センター(JACSES)プログラムコーディネーター 田辺有輝氏
「GPIFの石炭投融資実態・民間銀行の海外石炭火力発電事業プロジェクト融資実態に関するレポートの紹介」
<FFGJレポート発表の背景>
脱炭素化を進めていくにあたって、石炭採掘だけではなく石炭火力発電の考慮も重要であり、IEA(国際エネルギー機関)のシナリオではエネルギー関連によるCO2排出は今年2017年がピークとなるべき、と言われています。また石炭火力発電所は一旦建設されると数十年にわたって運転が想定され、また莫大な投融資をもとに発電プロジェクトが進められるため、銀行融資が果たす役割は大きなものです。そのため、石炭火力発電プロジェクトを考えるにあたって、銀行融資を最重要視している、とのことでした。
金融業界における関連する直近の動きとして、世界2番目の年金基金であるノルウェー政府年金基金が6月、投資先金融機関のポートフォリオに基づくCO2排出量開示を求めると発表しました。この年金基金は多くの日本大手企業の1%以上の株式を保持していることから、大きな影響を与えることが予想されます。また欧米系の銀行では石炭火力発電事業への投融資を禁止する動きが活発化しています。
<GPIFに関するレポートの紹介>
調査の対象となる企業は次の二つのリストによります。
1. ノルウェー政府年金基金が特定した石炭関連企業である、活動の3割以上が石炭関連である発電企業
2.石炭資産を保有している企業リスト(The carbon underground)に入る企業
これらの企業に対するGPIFからの投融資額の調査を行なった結果、計1兆7955億円の投融資がされていることが判明しました。GPIFは1兆円のESG投資をすることを宣言していますが、それ以上の額を石炭関連に投資していることになります。レポートの発表後にGPIFと議論をしたものの、運用によって生じうる民間活動への影響に留意する、との原則により、石炭セクターという特定の事業を除外することはできない、と回答されました。
またGPIFはESG投資3指数(2つの総合ESG指数と1つの社会関連指数)を公開していますが、先進国で2番目の国内外石炭関連事業をもつ丸紅のほか、出光興産・中部電力・関西電力・九州電力が優良企業とされているなど、石炭関連においては企業の選定に問題があるとのことでした。
<海外石炭火力発電プロジェクトへの投融資に関するレポートの紹介>
これまで他の機関からも複数のレポートが出されていますが、それらは企業単位での評価であり、個別プロジェクトベースでの評価を行っている点で新しいレポートとなっています。JBIC・NEXIのプレスリリースをもとに評価を行なった結果、三菱UFJ・三井住友・みずほの順に投融資額が大きくなっています。みずほの投融資額が低くなっている要因は、途上国石炭発電新規事業への投融資を行う際に、プロジェクトを統括するプラントメーカーごとに投融資する金融機関が異なっており、三菱・日立の案件では三菱UFJ、東芝のでは三井住友、商社などのプロジェクトファイナンスにおいては種々の銀行の連合、となっているためのようです。
このように、石炭への投融資を削減していく世界の潮流とは逆行した日本の金融機関の投融資の実態が明らかになりました。この現状を変えるべく、各金融機関には石炭関連の投融資をやめるよう提言するとともに、実際にやめてもらうよう金融機関へのメッセージを送ることが重要である、と話されていました。
講演4.レインフォレスト・アクション・ネットワーク(RAN)日本代表部 川上豊幸氏
「金融機関に対するエンゲージメントによるインパクト事例」
<RANの活動の背景・現状>
川村氏・松原氏のお話の通り、投資では低・脱炭素化にむけた大きな流れができているとのことでしたが、銀行の融資についてはまだ問題のある部分が多く、RANではその点に注目しています。RANには森林プログラムと気候変動・エネルギープログラムの大きく2つのプログラムがあり、森林プログラムでは紙・パーム油・ファイナンスについて、気候変動・エネルギープログラムでは金融について重点的に活動しています。両プログラムで金融を活動対象にしているのは、従来のような買い手の事業会社への働きかけだけでなく、金融機関からのプレッシャーも重要だ、と考えるためです。
そもそもこれらを始めたきっかけは、チャド・カメルーンにある石油パイプラインが森林破壊・住民の人権侵害を行っていた問題で、そのプロジェクトにCITI Bankによる融資が行われていており、その開発を中止させるために融資をやめるよう運動を行なったことでした。その後は石炭業界のレポートカード、石油パイプライン事業への活動などを行なっています。これらの活動の成果として、Bank of Americaによる石炭輸出禁止へのコミットメント、CITI Bankの環境政策導入など、多くの銀行の投融資政策・融資停止を勝ち取っています。直近の活動では、石炭・オイルサンド・深海石油開発・アメリカからの天然ガス輸出を対象とした「エクストリーム化石燃料」に関するレポートを発表されました。その結果を見ると、日本の金融機関は軒並みF評価であり、中国の金融機関と同じレベルにとどまってしまっています。
<日本における森林のファイナンスに関する活動の紹介>
森林保全は気候変動の観点からも非常に重要であると指摘されました。というのも、産業革命以降のCO2の1/3が森林減少に由来しており、森林伐採・劣化の防止などの森林保全によって30%の排出量削減が可能であるそうです。加えて、熱帯林に分布している泥炭地を開発することによるCO2排出も大きな問題となっています。泥炭地では水面下に植物の死骸由来の炭素が大量に蓄積されており、泥炭地開発における抜水の際にCO2として放出されるため、520万haの総面積から石炭火力発電所70基分に相当するCO2排出が生じる可能性があります。また丸紅がインドネシアで行っているパルプ開発から森林・泥炭地火災が発生し、大気汚染などが大きな問題となりました。このように、石炭だけでなく泥炭地開発も座礁資産となりうると仰っていました。
これらの問題を食い止めるため、金融機関の株主に向けたレポートやデータベースを作成・公表しています。それらの中ではパーム油・紙パルプ・天然ガス・木材に関する問題企業に対する融資額をまとめており、メガバンク3行からの融資額121億ドルにのぼるなど、日本の金融機関からの融資額が最も多く、次いでマレーシア・中国・インドネシア、と続いています。
<これまでの活動の成果と課題>
海外では銀行の融資政策導入などの成果が得られています。その一方、日本では透明性を求めているもののあまり取り組みが進んでいません。特に泥炭地開発が座礁資産となってしまう可能性について強く働きかけており、金融機関でもCSR担当者レベルは興味・問題意識を持つことが多い一方、マネジメントレベルにまで届かない現状があります。そのため金融機関への投資家側から働きかける方が早いのではないかと考えています。このような活動は成果が出るまで時間がかかってしまいますが、CFD・パリ協定などを受けて金融業界にも動きが見えてきているのでさらに加速させたい、とのことでした。
質疑応答
Q1.
石炭火力及び座礁資産リスクに関する世界的な動向の話がある中、なぜ日本や韓国の政府が未だに融資をしようとするのか、登壇者の皆様の見解を聞きたい
A1.
(川村氏)単純にそれらの政府が鈍感なだけではないでしょうか。気付かないとリスクは認識できないものであり、5~10年はこのままでよいと考えているように思います。正直リスク認識が相当甘いと言わざるを得ません。今年の筑後や昨年の北海道など豪雨がありましたが、それらが普通になって、慣れてきてしまっており、気候変動リスクと結び付けられていないと感じます。金融機関やステークホルダーが言わないとわからないでしょう。
(松原氏)企業がサステナビリティを考えずに足元のフローだけを考えすぎているのではないでしょうか。企業の社長の任期は3~5年と短いため、その間の成果をあげたいと考えると長期のリスクを軽視してしまうため、まず企業全体のガバナンスから変革し、続いて考え方の変革、そして長期の視点の導入、と徐々に変えていくことが重要です。加えて投資家も長期の視点を欠いており、考え方を変えるべきです。
(田辺氏)発電事業者とプラントメーカーの考え方の違いのためでしょう。発電事業者は運転開始から終了までの40~50年間について考えなければならないため長期を考えます。一方でプラントメーカーは建設計画を受注する、つまりプラントを売ればその後のことは関係がないため、短期しか考えません。今の日本などではプラントメーカーに重きが置かれているため、短期重視になってしまっているのではないでしょうか。
(川上氏)海外での案件はJBICやJICAなど政府機関のバックアップがあって損がないためにそれに乗っかっており、また国内でも政府の動きが緩いと感じられることが原因ではないでしょうか。本来は40年後を考えて判断すべきですが、リーマンショックのときのように気づく人は気づくが気づかない方が当面穏やかな生活が続くため、現在は長期の判断がされていません。やはりガバナンスなどについてきちんと主張する人が必要です。
Q2.
話に上ったノルウェー、カリフォルニアの年金基金のダイベストメントについて、背景には議会の動きがありましたが、日本の国内での国会の動きなどはないか
A2.
(松原氏)GPIFについて、現行法律ではESGの個別課題に立ち入ることは不可能です。そのため、PRIに署名していることを使って働きかけるなど、投資機関がエンゲージメントしていく必要があります。
(田辺氏)気候変動政策においては共産党が1番熱心であり、議員レベルでは民進党に一部関心のある方がいるものの、全体的には残念な現状です。
(川上氏)GPIFの管理・運用方法については議論があります。
Q3.
石炭からのダイベストメント後のエネルギー需給について意見をききたい
A3.
(川村氏)燃料用途・材料用途ともに化石燃料はいずれ座礁資産化し、再生可能エネルギー(再エネ)しかないでしょう。それに向かう流れとして、ゼロエミッションビークル(ZEV)含め使う方がどう変わっていくか、不安定な電源のマネジメントとして分散型エネルギーにどう変化させるか、ゼロエミッションビルディング/ハウス(ZEB/ZEH)がマーケットにどう普及されていくかなど、再エネのfeasibilityの議論が重要です。
(松原氏)投資家はエネルギー政策の議論をせず、経営としての様々なリスク側面の一つとしてのCO2排出の認識の話が中心になっています。
(田辺氏)現在の新規導入の6割が再エネであり、その傾向を更に進展させて、電力全体での再エネの比率をあげていくことが重要です。
(川上氏)再エネしかない一方で、安価なパーム油を発電に使うなど、バイオマスが森林破壊に結ばないか懸念しています。
Q4.
1)TCFDの提言を受けた11社の銀行の判断などを念頭に、投資や融資先企業における情報開示をどう思っているのか
2)Science Based Target(SBT)についてりそな銀行はどう考えているのか
A4.
(松原氏)
1)エネルギー・素材企業は自然資本を利用しているなど、企業・業種によってマテリアリティーが違うため、マテリアリティーを設定した理由やそれを受けてのKPIなどについて対話を行なっていきます。またチャレンジな話にはなりますが、政府系銀行にも働きかけるべきだと考えています。
2)Scope1からScope3への移行を重視しており、気候変動についてはカーボンディスクロージャープロジェクト(CDP)に未回答の企業へその理由やリスク認識に関するレターを書いています。特に業種によってはScope1よりもScope3の方が排出量が多いこともあり、Scope1だけではいいかどうか判断しにくいため、できるだけScope3に従ってほしいと考えています。今後はターゲットを持っていない企業がどういう取り組みの中でそれを実現しようとしているのかが重要であり、情報開示の質と量をあげていきたいです。
2017-08-25